私たち、株式会社トレジャーフットでは、事業共走部・地域共走部・金融事業部という3つの事業部が、日々お客様の課題解決に向けて様々なプロジェクトを進行しています。
事業共走部をひと言で表すと、「企業とプロ人材が、一緒に汗をかきながらゴールに向かって走り切るための伴走者」です。
前回の記事では、事業共走部が行う支援や、今後の展望について語りました。
今回は、事業共走部が普段どのようなスタンスで企業と向き合い、どんな価値を届けているのかを部長である武田が本音で語りました。

===
事業共走部 部長 武田 昌大
1985年秋田県北秋田市出身。立命館大学卒業後、デジタルコンテンツ業界に従事。人口減少・高齢化が著しく進む故郷に危機感を感じ、2011年起業。秋田と東京の二拠点居住をしながら、米のネット販売や飲食店の立ち上げ、関係人口創出など地域課題解決に取り組む。地方での働き方に課題を感じ、模索する中でトレジャーフットと出会う。総務省地域力創造アドバイザー。日本で最初にクラウドファンディングに挑戦した6人のうちの1人。
===
コミュニケーションの起点は「お客さまではなく、友人になる」こと
――まずは、事業共走部の支援を語るうえで欠かせない「コミュニケーション」について教えてください。初対面のお客様と、どのように距離を縮めているのでしょうか。
武田:誰でも、初めて会う人って少し構えてしまいますよね。特に地方の老舗企業の社長さんになると、長年たくさんの営業を受けてきていて、「営業の電話は全部断っています」という方も少なくありません。そういう方に、いきなり「支援させてください」と言っても、心の扉は開いてもらえません。
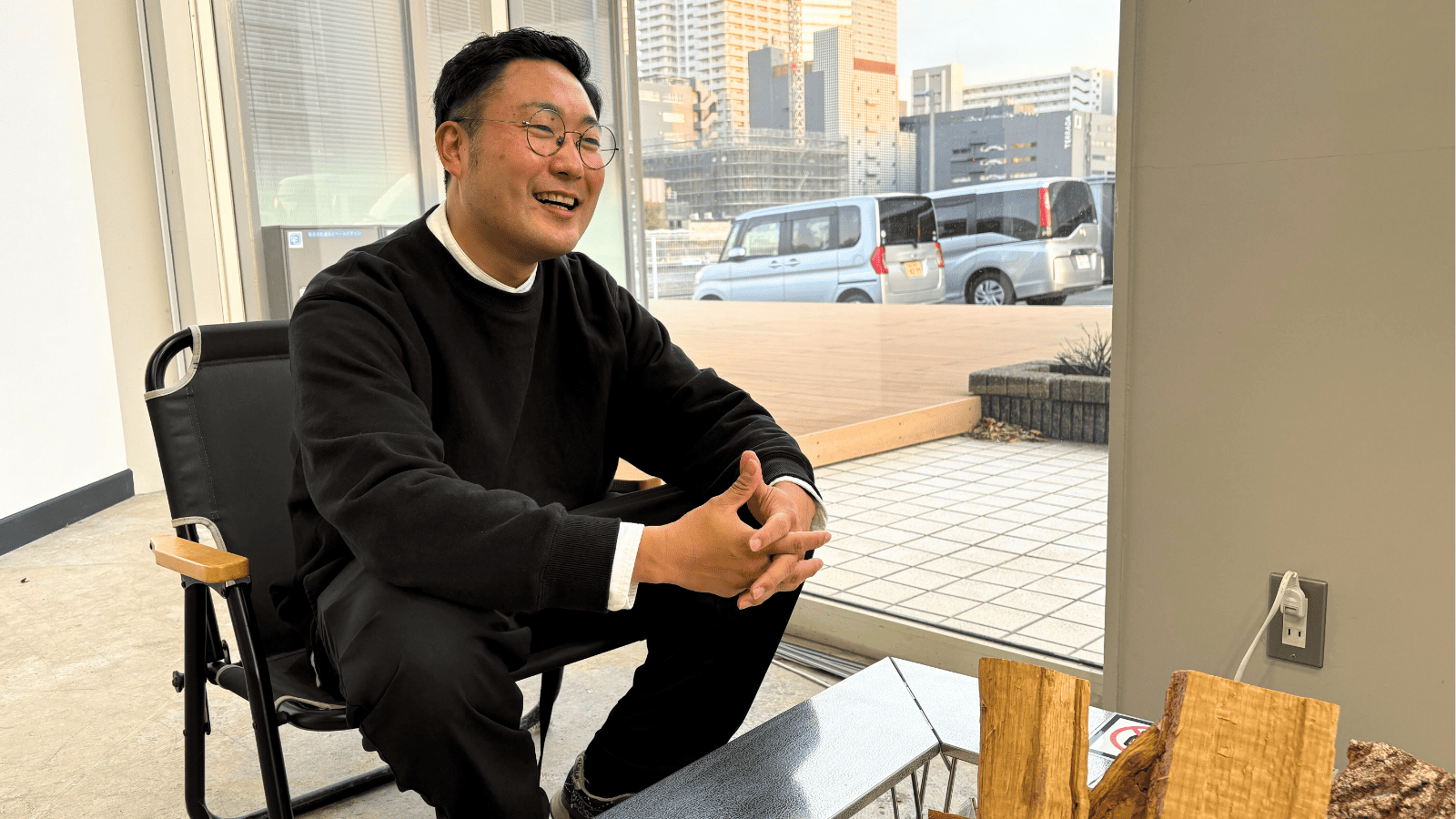
だから私は、「お客さま」としてではなく、「友人になりたい人」として接するように意識しています。
LINEの交換も、「営業の連絡先」ではなくて、「普通に友達としてつながる」感覚です。向こうから自然にLINE登録してもらえるくらいの距離感をつくることを目指しています。
そのために大事にしているのが、リスペクトを持ちながらもフランクに話すことです。相手の仕事や商品を心から「すごいですね」「おもしろいですね」と感じて、その場でちゃんとリアクションをする。
たとえば豆腐屋さんに伺ったときも、食べてみて本当においしければ、「これめちゃくちゃおいしいですね!」と全力で伝えます。逆に、社長の悩みやしんどい話を聞いたときは、「それは大変ですね」「わかります」と、ちゃんと共感して受け止める。
そうやって、相手の想いにきちんと反応すること自体がコミュニケーションだと思っていますし、この距離感を大切にしたいと思っているんです。
「好きになる」ことから始まる支援
――そうした関係づくりは、どのように事業共走の支援につながっているのでしょうか。
武田:まず、コミュニケーションを通じて、その会社や商品を「好きになる」ことから始めます。私自身、これまで自分でも事業をやってきて、「いいな」と思ったものは人に伝えたくなるタイプなんです。
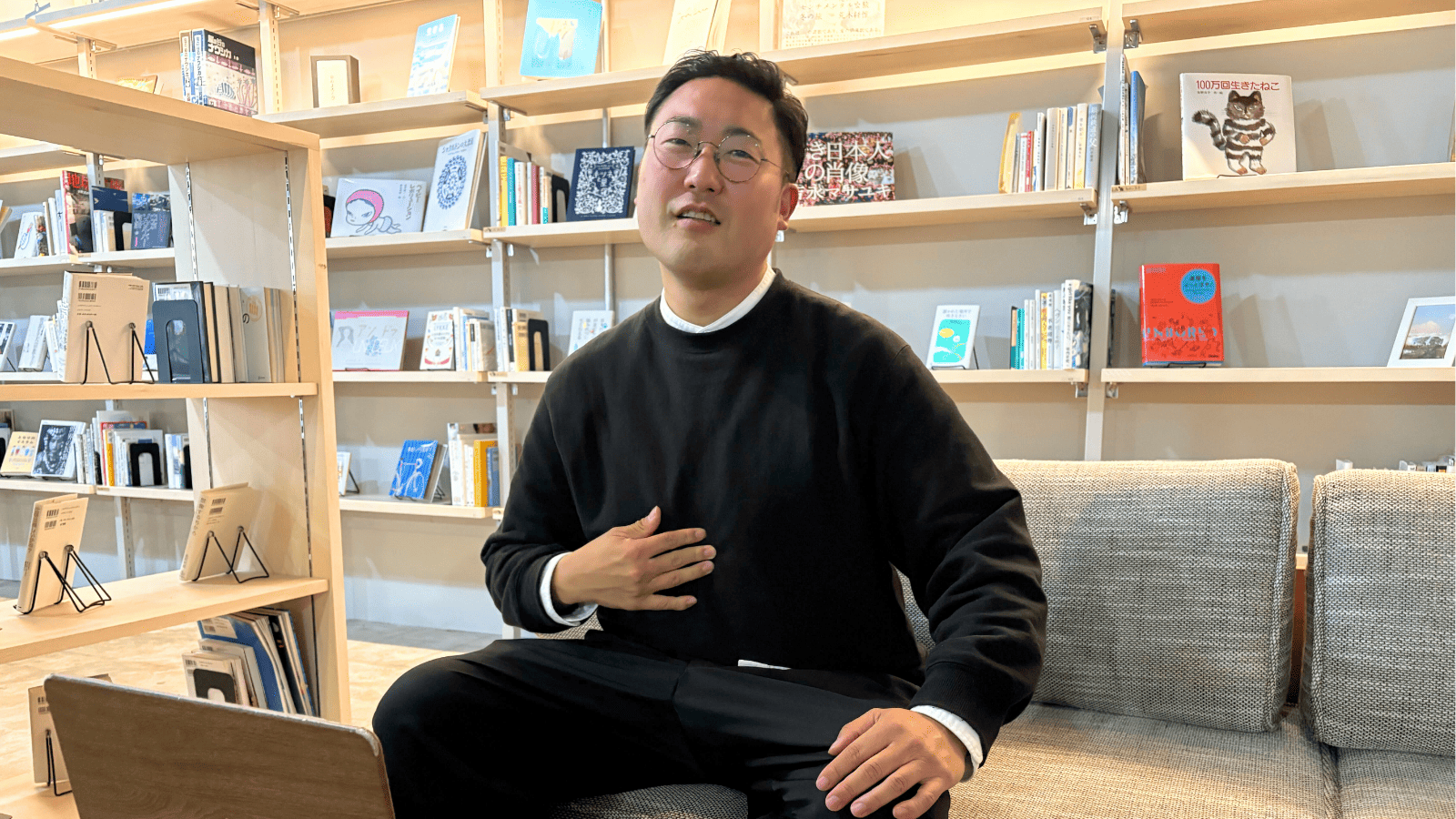
ですから、企業さんと出会ったときも、「この会社の素敵なところは何だろう?」「この商品の魅力はどこにあるんだろう?」という“いいところ探し”を徹底的にやります。
同時に、「こんなに良い商品やサービスを提供しているのに、なぜ今はまだ売れていないんだろう?」という課題にも向き合っていきます。もちろん、この課題への考え方は商品やサービスの売上だけにあてはまる訳ではありません。人事や採用、ブランディング、事業戦略など企業の抱えるすべての課題で、上記のように考えているんです。
好きになり、課題を深掘りする。そして、どのような提案をすれば課題を解決できるのかを一緒に考える。この一連のプロセスまで含めて、事業共走部の支援だと考えています。
結局、「この商品をもっと多くの人に知ってほしい」「この社長の想いを一緒に届けたい」と自分ごと化できるかどうかが、支援の質を左右するのだと思います。
三者で汗をかき合うことが「共走」
――トレジャーフットでは「共走」という言葉を大切にしていますが、武田さんにとって「共に走る」とはどんな状態でしょうか。
武田:「誰か一人だけが頑張る状態ではないこと」だと思っています。
社長だけが頑張るのではないですし、一緒に支援をしてくださるプロ人材だけが頑張るのも違います。もちろん、私たちトレジャーフットだけが頑張る状態も政界ではありません。
三者それぞれが足りないところを補い合って、みんなで汗をかいている状態が「共に走っている状態」だと感じます。
イメージとしては、歯車がいくつもかみ合って回っている状態です。
社長、プロ人材、トレジャーフット、それぞれが役割を持った歯車で、どれか一つでもかみ合っていないと、プロジェクト全体は前に進みません。
だからこそ、「今、誰か一人に負荷が寄りすぎていないか」「どこかの歯車が空回りしていないか」を常に確認しながら、全員で走っていける状態を作ることを大事にしています。
ただのコンサルティングではなく「共走型支援」である理由
―― 一般的なコンサルティングと比べて、トレジャーフットの事業共走部による支援にはどのような違いがあるのでしょうか。
武田:よくあるコンサルティングだと、「課題を分析し、提案書を出して終わり」というケースも多いと思います。一方で、トレジャーフットの事業共走部による支援は、提案して終わりではなく、一緒に現場でやり切るところまで関わる点が大きく違います。
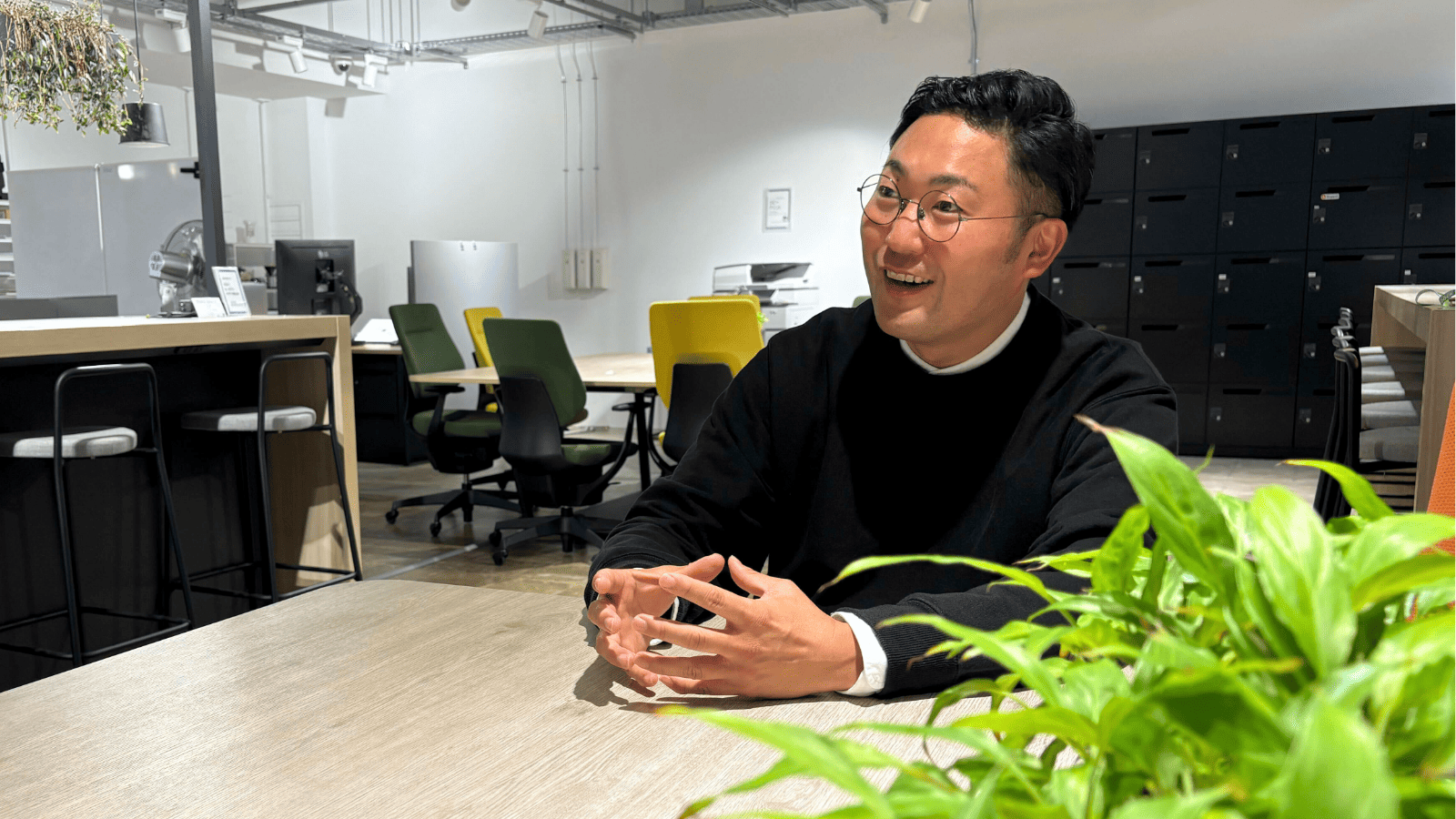
この現場部分に、弊社でご登録いただいている、5,000名を超えるプロ人材の力を借りていきます。プロ人材の方々は、多くの場合、自社とは違う業界や規模の会社での経験を持っています。
その知見を活かして、「この会社にはこういう打ち手が合いそうだ」「このやり方なら現場でも回せそうだ」と、具体的な手を一緒に考えてくれる存在です。
企業側からすると、社内だけでは持ちきれないリソースや経験値を、外部のプロ人材とトレジャーフットのチームで補完していくことができます。
「社内だけでは届かないところまで、一緒に手を伸ばしてくれる」のが共走型支援の価値だと感じています。
――今後、ホームページなどを見て支援を検討される企業も増えていくと思います。そうした企業にとって、事業共走部の支援で一番大事なポイントはどこでしょうか。
武田:一番大事なのは、ゴールがずれていないかを常に確認することだと思っています。
プロジェクトには、社長、現場のメンバー、プロ人材、そしてトレジャーフットと、様々な立場の人が関わります。それぞれが「このプロジェクトはこうなるといいな」という期待を持っているのですが、そのイメージが少しずつ違っていることがあるんです。
だからこそ、進行の途中で何度も立ち止まりながら、「当初のゴールからずれていませんか?」「みんなが目指している方向はそろっていますか?」と、認識を合わせていくことが重要です。
表向きの要望だけでなく、「本当はここに不満がある」「実はここが不安だ」といった本音も含めて吸い上げながら、同じ方向を向いて走り続けられるように調整する。それが、事業共走部の大切な役割だと考えています。
マッチングで一番大事なのは「スキル」ではなく「バイブス」
――企業とプロ人材の間に立つ立場として、特に意識していることはありますか?
武田:僕はよく「バイブス」が大事だと言っています。
プロ人材がどれだけ優秀なスキルを持っていて、課題とのマッチングが完璧だったとしても、社長との相性が合わなければ、その人は100%の力を発揮できません。
逆に、多少経験が足りなくても、社長と価値観やテンポが合っていて、「一緒にやりたいですね」と素直に言い合える関係であれば、プロジェクトは前向きに進んでいきます。
ですから、マッチングの際には、スキルや経験、業務の適性だけでなく、人柄やコミュニケーションの雰囲気、価値観の近さといった部分も含めて判断しています。
社長とプロ人材の「波長を合わせていく」ことこそ、私たちが担っている大きな仕事の一つだと思っています。
「すべての縁を大切にする」事業共走部の価値観
――事業共走部のチームの雰囲気についても教えてください。
武田:一言で言うと、笑顔が絶えない、話しかけやすいチームです。
誰かの「部下」というより、「一つのチーム」としてコミュニケーションができている感覚があります。DJがいたり、おにぎり屋さんをやっているメンバーがいたり、三人のパパがいたり、自分でフットサルチームを運営しているメンバーがいたり……
まさに個性のドッジボールのような集まりです(笑)。
そんな事業共走部が大切にしている価値観が、「一縁(いちえん)も逃さない」というものです。「1円」ではなく「一縁」。すべてのご縁を大切にする、という意味を込めています。
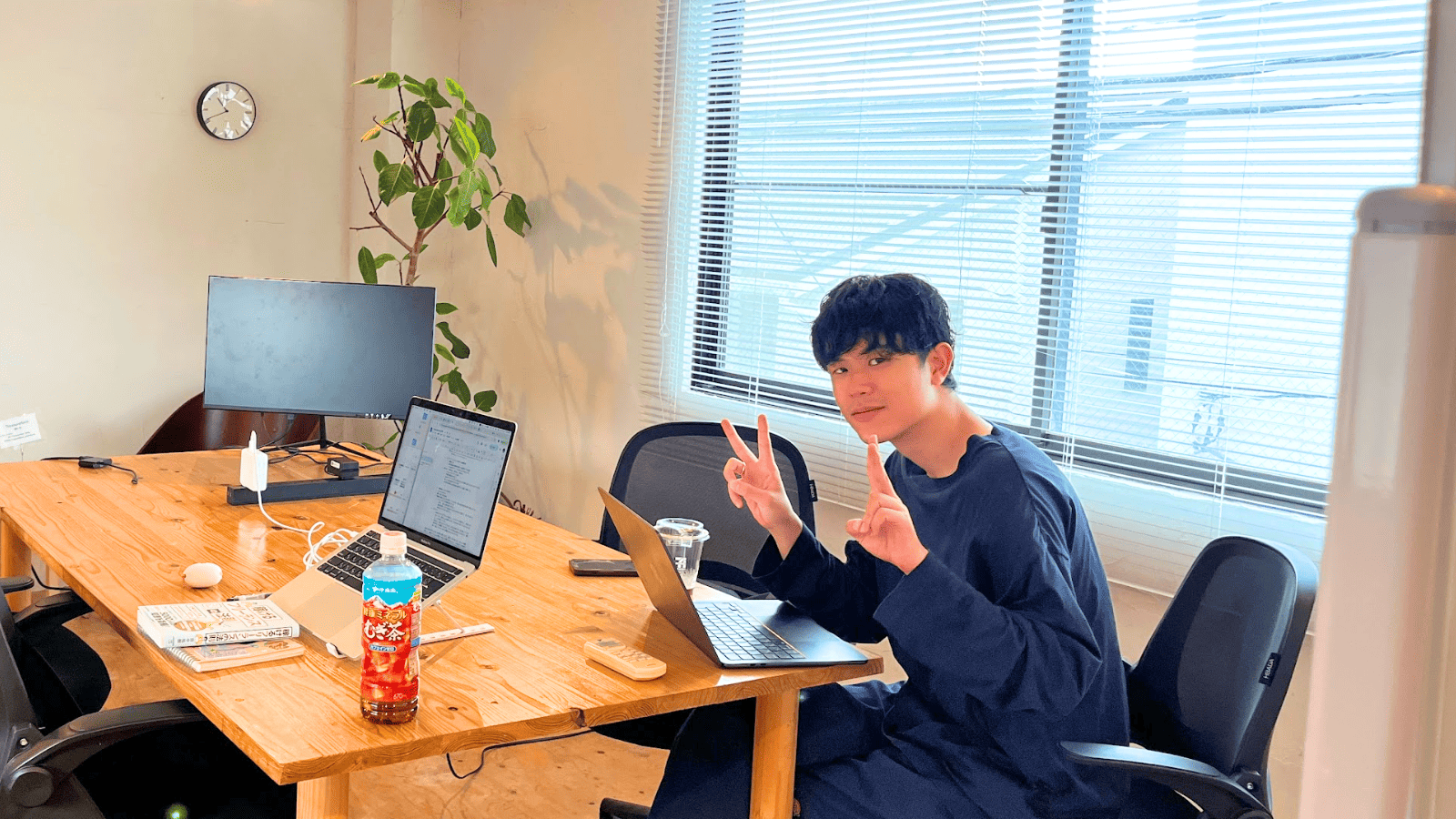 お金の多寡だけで判断するのではなく、「このご縁をどう活かせるか」「このつながりをどう未来につなげていけるか」を考える。
お金の多寡だけで判断するのではなく、「このご縁をどう活かせるか」「このつながりをどう未来につなげていけるか」を考える。
人が好きで、ご縁を大事にできる人たちが集まっているチームでありたいと思っています。
――2025年4月からスタートした「チームアップ」の取り組みについても教えてください。
武田:まだ発展途上ではありますが、今後は1社に対して2名以上のメンバーで伴走できる体制をつくっていきたいと考えています。
これまでは、事業共走部の人数も4〜5人程度で、1社に対して1人が中心となって支援するケースが多くありました。ただ、その場合はどうしても支援の手厚さに限界がでてきてしまいます。
メンバーが少しずつ増えてきた今だからこそ、戦略や全体設計をメインで見る人、現場の実装や日々のコミュニケーションを支える人、といった形で、役割を分担しながら1社をチームで支えるスタイルに挑戦していきたいと思っています。
そうすることで、企業側も「この人にしか聞けない」ではなく、「このチームに相談すれば大丈夫」という安心感を持てるようになるはずですし、プロジェクトとしても厚みが増していくと感じています。
最後に
企業とプロ人材のあいだに立ち、ゴールをすり合わせながら、バイブスまで含めてマッチングしていく。
そして、「ひとつのご縁も逃さない」という価値観を胸に、関わる人たちと共に走り続ける。
それが、株式会社トレジャーフット事業共走部のサービスのあり方です。
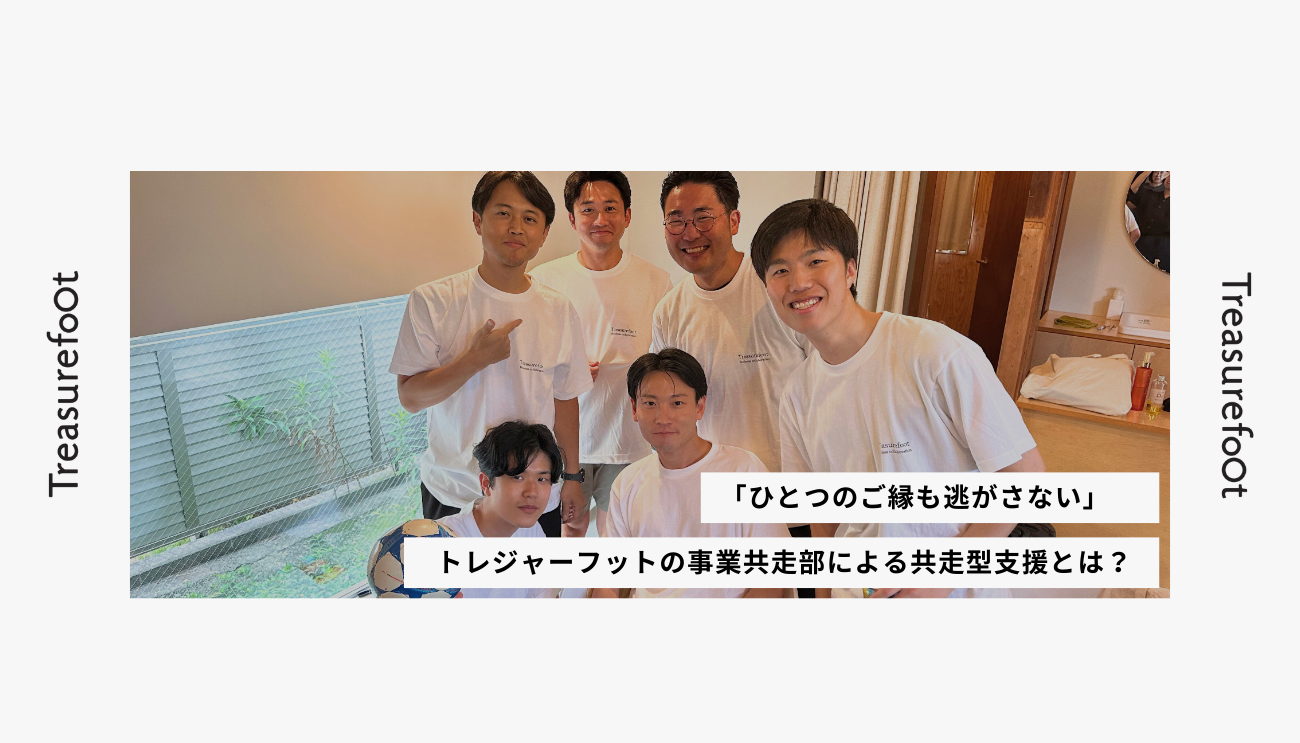

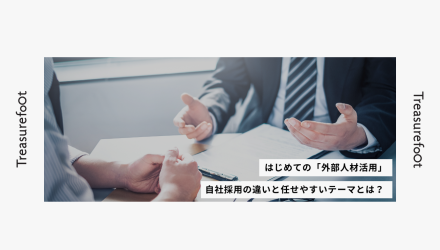




 まずは無料で
まずは無料で お問い合わせ
お問い合わせ イベント情報
イベント情報