はじめに
2025年3月4日、有楽町のPatia西新橋にて、「ここから、しまね vol.3」が開催されました。今回のテーマは「津和野の暮らしとお茶」です。

ゲストには、島根県津和野町で老舗のお茶屋「香味園 上領(こうみえん かみりょう)茶舗」を営みながら、日本遺産地域プロデューサーや観光戦略プランナーとしても活躍するリコッタ(上領)瑠美さんをお迎えしました。イベントは終始リラックスした雰囲気で進行し、参加者との距離がぐっと縮まる、あたたかなひとときとなりました。
瑠美さんが選んだ生き方──暮らしの中に、仕事がある
リコッタ(上領)瑠美さん/香味園 上領茶舗代表・日本遺産地域プロデューサーほか
大阪生まれ、東京で広告業界に勤めていた瑠美さんは、父親の病気をきっかけに、人生の大きな転機を迎えます。
「このままでいいのか?」という問いが心に芽生え、彼女が目指したのは“暮らしの中に仕事がある”という新しい生き方でした。父の病に向き合うことで、初めて立ち止まり、自分にとって何が本当に大切なのかを見つめ直したといいます。
津和野という町との“再会”
祖父母が暮らしていた津和野は、幼い頃から帰省のたびに訪れていた町です。
“特別”というより“当たり前”だった風景を、フランス人の夫が「ここに住みたい」と言ったことで、彼女の視点がガラリと変わりました。
「言われてみれば、確かに美しい」
それは、見慣れた風景の中に、新しい価値を見出した瞬間でもありました。
家業のお茶屋を、今の時代にアップデート

当初は「自分が継ぐなんて想像もしていなかった」と語る、瑠美さん。
90年以上続く老舗のお茶屋「香味園 上領茶舗」は、時代の流れとともに少しずつ厳しさを増し、閉業も現実的な選択肢のひとつとして考えていたといいます。
それでも彼女が継業を決意したのは、町の風景や、家族とのつながりを未来に残したいという想いがあったから。代々受け継がれてきたお茶文化に、今の時代の息吹を吹き込もうと、カフェや宿泊施設を立ち上げ、日本遺産の地域プロデューサーや観光戦略プランナーとしての活動もスタートしました。なかでも注目を集めたのが、津和野の伝統茶「ザラ茶」と、フランスのハーブティ文化「ティザンヌ」を掛け合わせた新たなスタイル。
ある晩、ザラ茶を飲んだフランス人の夫がふと口にしたひと言は、
「これ、ティザンヌ・ジャポネだよ」というものでした。ティザンヌとは、ハーブや果実を使った“ノンカフェインの養生茶”のこと。体調や気分に合わせて選ぶ、フランスの暮らしに根づいたお茶文化です。
そのスタイルをヒントに、ザラ茶を“自分だけのお茶”として提案するアイデアが生まれました。
地元に根づく伝統の味が、時代を超えて再び息を吹き返す——。
そんな希望に満ちた挑戦が、参加者の心に静かに響いていました。
移住後に感じた、都会と地方のちがい

「都会は誘惑が多い。地方には選択肢が少ないけれど、それがむしろ楽なんです」と、瑠美さんは語ります。東京で働いていた頃は、朝から晩まで予定が詰まり、気づけば終電、気がつけば朝。選ぶ自由がある反面、「何を選ぶか」に疲れていたことに、後から気づいたといいます。
津和野での暮らしは、それとは対照的でした。朝は太陽の光で目覚め、夕方17時には町が静かに1日を終える。
店も人の動きもぴたりと止まり、自然と暮らしにリズムが生まれていきます。
「夜遅くまで保育園に子どもを預けることも、コンビニに行くこともできない。でも、だからこそ、自分の時間の使い方に素直になれるようになりました」
便利さが当たり前だった都会とは違い、津和野では人と人との距離がぐっと近くなります。誰とすれ違っても「こんにちは」と声が届く。そんな関係性が、暮らしのなかに自然に溶け込んでいます。子どもたちは地域の“大人たち”に見守られ、年配の方と若い家族が、ひとつのプロジェクトでチームになることも珍しくありません。
「この町では、起きることすべてが“自分ごと”になるんです」
それは、効率やスピードとは別の豊かさ。
「暮らしの中に仕事がある」という、瑠美さんが思い描いていた理想が、静かにかたちになっていったのです。
これから何を、どうしよう?

「この町を元気にしたい。小さな成功体験を積み重ねて、もう一度みんなが挑戦できる町にしたいんです」そう語る瑠美さんの声には、静かな優しさと、揺るぎない意志が込められていました。
少子高齢化や観光の低迷など、津和野が抱える課題は決して小さくありません。
けれど、「どうせ無理」と諦める前に、「一歩踏み出せば変わるかもしれない」と、行動で示してきたのが瑠美さんです。
子どもから高齢者までが関わる“チーム津和野”として、世代を超えて町を動かしていく──そんな未来を、彼女は本気で描いています。
印象的だったのは、旅人とのひとつの出会い。
ある日訪れたお客様に、瑠美さんの娘さんが手紙を手渡したことがありました。
その素朴なやりとりが心に残り、旅人は後日、再び津和野を訪れてくれたといいます。
「旅のハイライトは、名所よりも“人との出会い”かもしれない」
そんな気づきを与えてくれる、小さなエピソードです。
今、瑠美さんが目指しているのは“誰かの記憶に残る町づくり”です。
そのために、自らを「バトンを渡す人」と位置づけています。
「継いでほしい」と願うのではなく、「継ぎたくなる未来を整えたい」と話す瑠美さん。老舗の香味園 上領茶舗の暖簾を守りながら、ザラ茶という伝統の味を、今の暮らしに合うかたちで提案し続けています。
旅人と町の人が交わる場所をつくり、地域の過去と未来、人と人をやわらかくつなげていく。それが、瑠美さんの描く「これから」のかたちです。
等身大の声に、真剣なまなざし

トークの後半は、参加者との質疑応答へ。
「ひとつの事業だけで生計を立てるのは難しくないですか?」という質問に、瑠美さんはためらうことなくこう答えました。
「うちも最初は、カフェだけでは正直厳しかったんです」宿泊業や文化財の活用、観光戦略など、複数の分野に関わる“マルチワーカー”として働き方を広げてきた自身の経験を、率直に語ってくれました。
さらに、「売れているものを真似するより、自分たちにしかない魅力を磨くことが、共感や注目につながる」と、実践に裏打ちされたアドバイスも。
「地方には“ないもの”が多いけれど、だからこそ自由に形をつくっていける」その言葉には、現場で積み重ねてきた経験と覚悟が滲んでいて、参加者たちも深くうなずいていました。
まとめ
“旅のハイライト”は、いつも人との出会い
イベントの最後に、瑠美さんはこう語りました。
「自分が楽しんでいることが、いちばん大事。そして、旅のハイライトは人との出会いです」
継業も町づくりも、誰かのためだけではなく、自分自身が心から楽しむこと。
そして「私は、バトンを持って次につなぐ人でありたい」と締めくくりました。
“関わりしろ”がある町・津和野。
瑠美さんの等身大の言葉に、参加者はあたたかい刺激と、未来へのヒントを受け取った夜となりました。
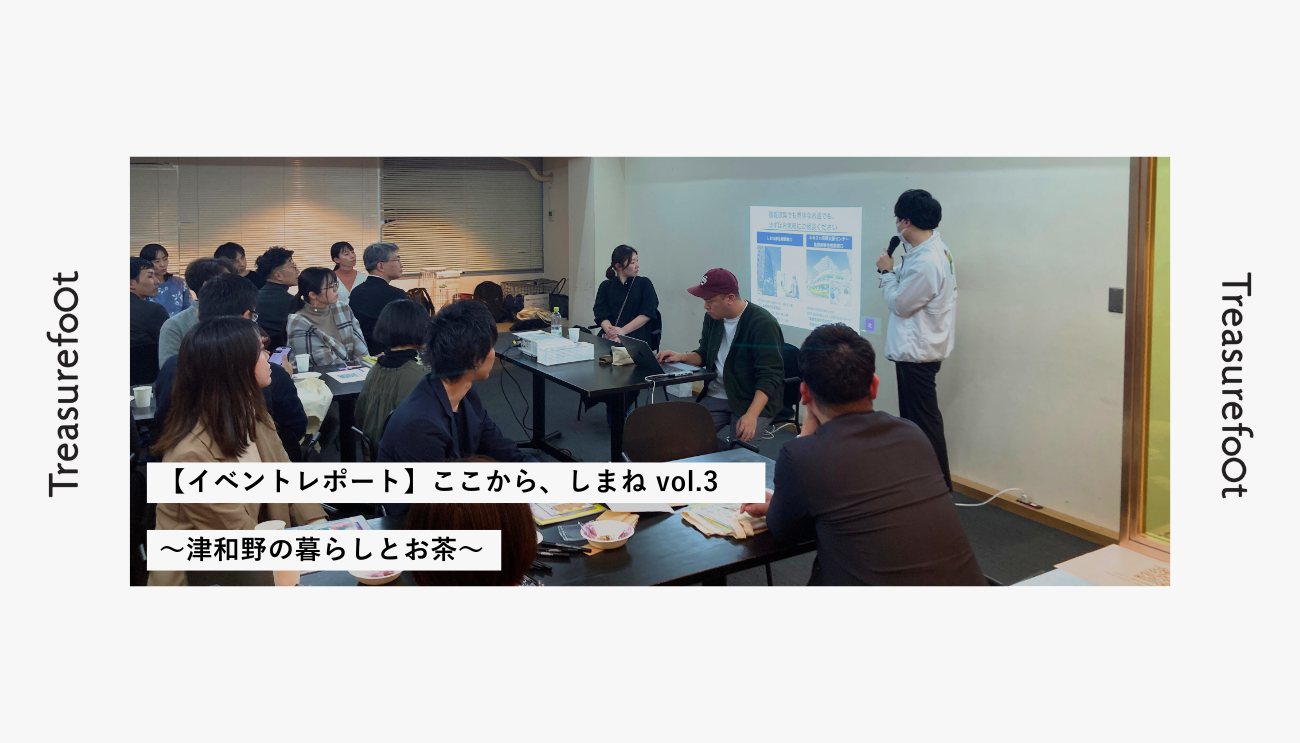
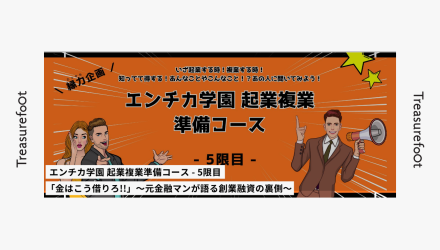





 まずは無料で
まずは無料で お問い合わせ
お問い合わせ イベント情報
イベント情報